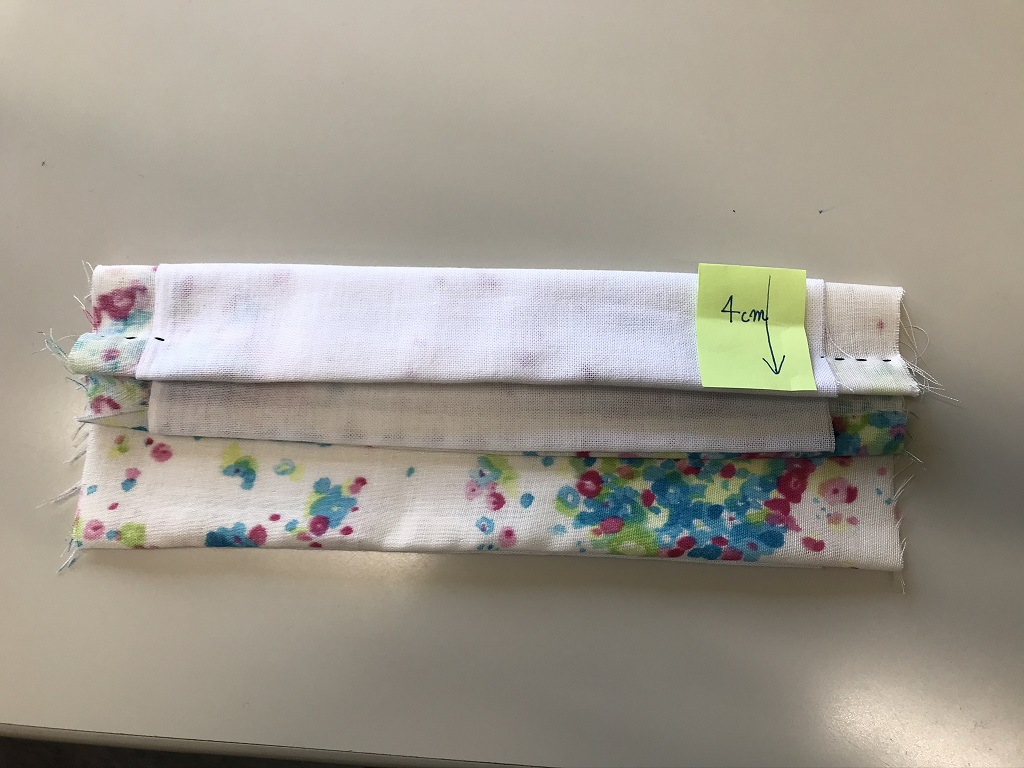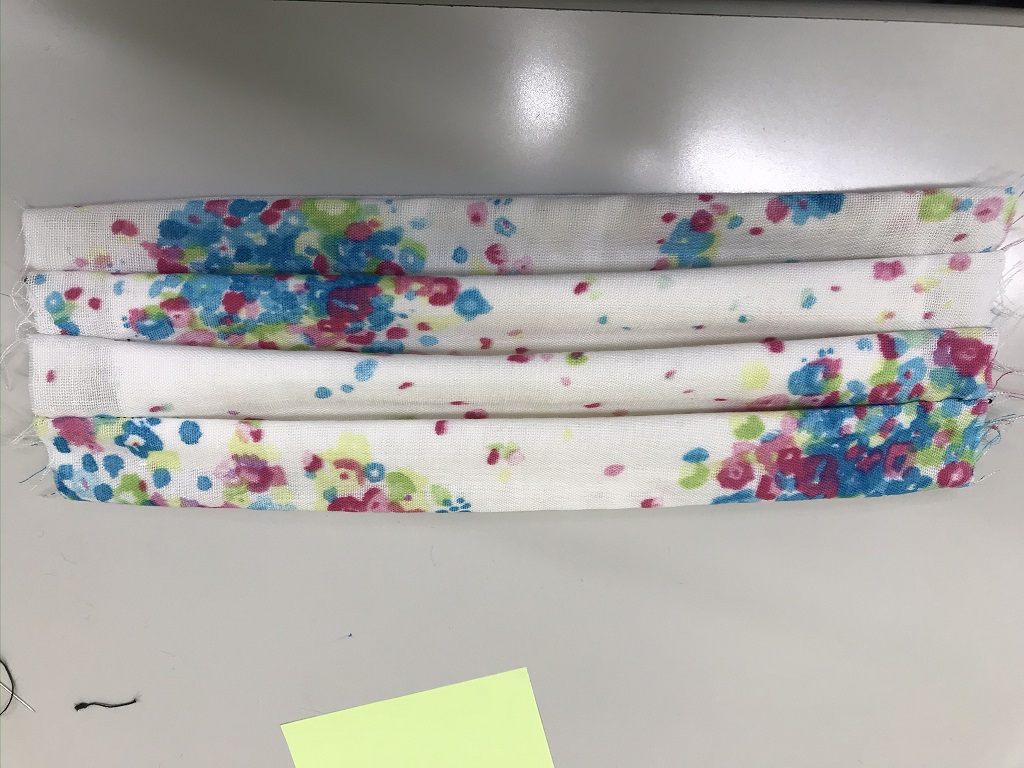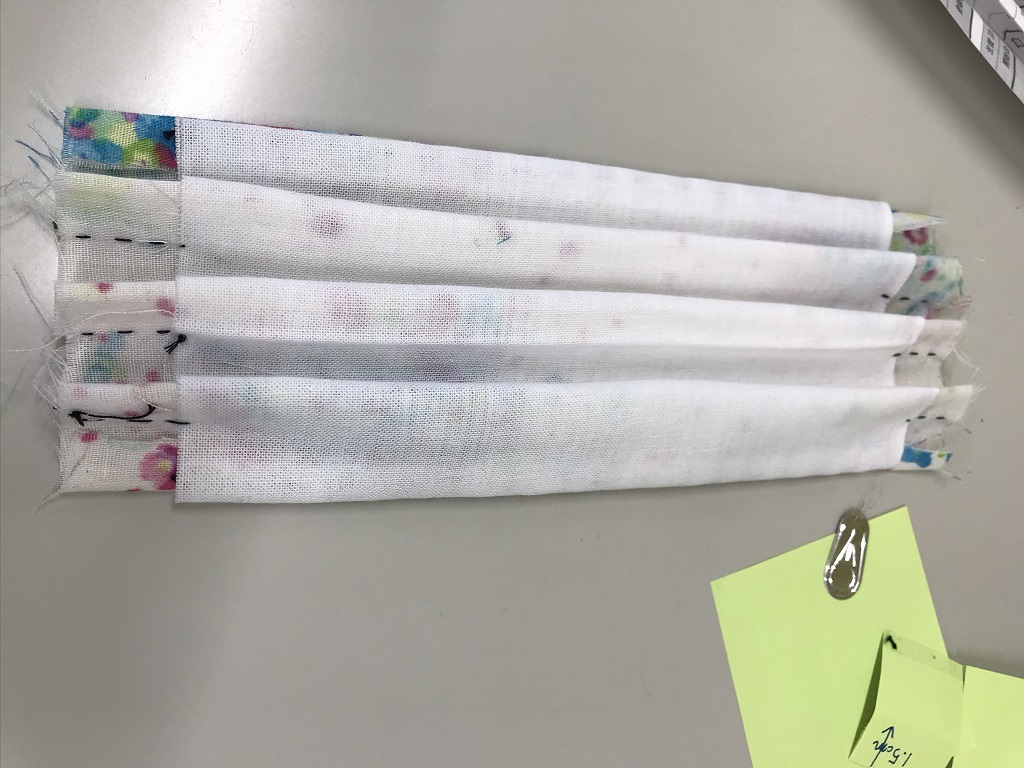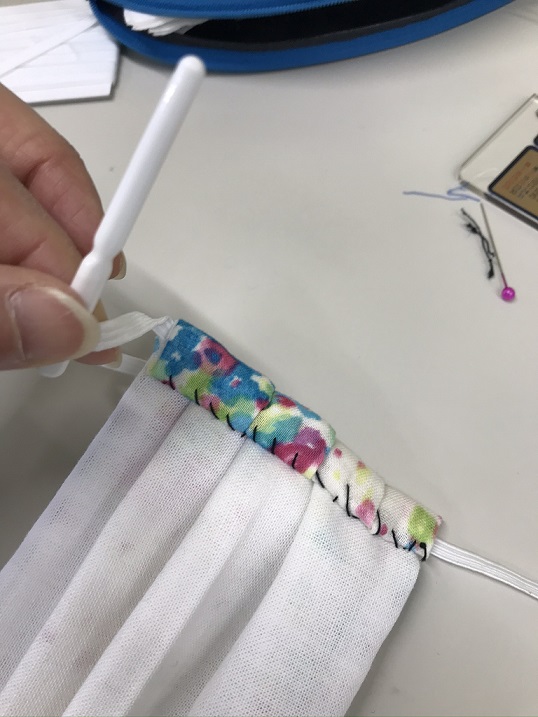2020年
3月
14日
土
2020年2~3月合併号 ~諸行無常~
自分は何でもなくなってから買いに行くタイプだ。
ともすれば必要であっても買わないことすらある。
恵まれた時代に育ったがゆえに欲しい物はいつでも手に入るのが常だと。
危機管理の甘さはおやつのカールや梅ジャムが店から消えた時思い知ったはずなのに!
しかし解決策を見つけ前向きに生きてきた。
無ければ知恵を絞って工夫すべし!
というわけでキーワード『トイレットペーパー代用品』でインターネット検索開始♥
『トイレットペーパーの代わりにできる9つ』にすぐさま目が留まった。
代わりの品とはいったい?!!
ひとしきり読んだ後近所の生活雑貨店へと走った。
まずは念のためにトイレットペーパーコーナーへ行ってみたが予想通り完売。
そしておもむろに文房具用品コーナーへ移動!
例の“代わりの品”を見つけて少々口元を歪めてみた。
まだ誰も気づいてないらしい。
それを暫く見つめていたが今日は買わずに帰った。
トイレットペーパーコーナーから躊躇なく文房具のノート(紙)コーナーへ移動して手に取るのも余りにも露骨だ…。つづく
2020年
3月
08日
日
2019年10~11月合併号 ~非常時~

10/11台風19号上陸前日。
テレビでは1日中『命を守る行動を!』とアナウンスが流れた。
想像を超える最大級の台風と知りつつなす術なし。
被害も想像を超えるのか…。
空が荒れぬ内に近所のスーパーへ買い出しに行った。
すでに品薄状態となっていたことに緊張が走った。
明日の停電や断水を想定し極力調理不要の食料を求めレトルト食品コーナーへ。
皆考えることは同じらしかった。
なんと高級レトルト食品ばかりが棚に残っていた。
仕方なく銀座カリー辛口、インドビーフカリースパイシーなど取りあえず6食分好みの辛さを間違えないよう注意してカゴに入れた。
お惣菜コーナーのコロッケ完売。
仕方なくちょっと高いけどカニクリームコロッケにしてみた。
揚げたてのフライや天ぷらも魅力的。
栄養価の高いチーズも今日だけはちょっと奮発してヤギのチーズに。
リラックスに欠かせない赤ワインも1本。
前から食べてみたかったお菓子もゲット。
ただの買い物を済ませ帰宅。
浸水対策とやらで雲隠れしていた七田が「いや~昔の写真って面白いよね~♪」
とヘラヘラしながら2階へ上がってきた。
さしずめ床に散らかしていたアルバムをめくっては目を細めていたのだろう。
非常時におかしな行動とるのは自分だけではないと判明。
写真の解説:
非常用に買い置きしてみたレトルトカレー。ではなくてレトルトカリー。赤ワインにもよく合う。
2017年
4月
10日
月
2017年4月号 ~復興のかたち~

東日本大震災から6年。
岩手県大槌町は津波にのまれ町が消えた。
以前教室に通っていた生徒さんも被災地に住む1人。
後に伺った間一髪助かったという体験話は忘れない。
多くの犠牲、明日からの衣食住の不安、ライフラインの全てが滞った。
復興に掛る歳月が並々ならないことを言うにはばかり、闇雲に復興を願うだけの6年が経った。
先日大槌からメールが届いた。
「町中に何件か家が建ちました。大半はまだ仮設(住宅)ですが。目に見えてきました。」
物理的で確かなものが目に見える喜び。
この短い文に目頭が熱くなった。
初めて“復興”の意味がわかった気がした。
駅や線路が再建して隣町へ行く電車が走って病院や喫茶店や商店がどんどん立ち並ぶといいねえ。
と声に出して言ってもいい気がした。
あの日から7度目の桜を見上げ、ウキウキしてもいい気がした。
はばかってばかりはいられない。
写真の解説:
球根から育(放置し)てたヒヤシンが3色見事に花咲きました。とてもいい匂いがしているところをパチリ!(2017.3.17撮影)
2016年
3月
24日
木
2016年 3月号 ~不自由しないと気付かない~

新聞の折り込みチラシを食い入るように見つめた。
『サバイバル緊急防災用品 この1袋が家族を守る』
袋の内容写真の隅に『48時間生き抜く』とあった。
え?たったの2日で“サバイバル”とは大げさなような気もするが、このように食いつく者がいると思えばネーミング効果は絶大だ。
しかし内容を見ると全て家にある物ばかり。
仮に無くても2日位困らない気すら…という考えは甘いのだろうか。
ふと1月の西日本大寒波襲来を思い出した。
19万世帯が水道管破裂により断水。
テレビで福岡県のある家族(おばあちゃんと小学生の孫3人)の密着取材が忘れられない。
寒空の下、給水車の受水を並ぶこと1時間半。
持参のポリ容器は水で満たされ重そうだ。
ようやく孫達と持ち運び帰宅。
コップに汲んだ水を各自少量ずつ手洗いに使う。買ってきたおにぎりとコロッケで夕食。
紙皿と割り箸を贅沢に使い捨てて後片付けをするおばあちゃんが言った。
「食器を洗う水はありません。いつ水道が復旧するのか不安です。」
このポリ容器の水が家族の命を守っているんだ!
割り箸と紙皿も!
真のサバイバルグッズだ。
おばあちゃんは炊事が嫌いなのかと余計な詮索をした己を恥じた。
翌朝七田が「防災袋を買おう!」と声高に、興奮気味に言った。
七田もやはりあのチラシを見たのだろう。
写真の説明:
3/24朝撮影。桜の蕾のピンクと黄梅の黄がとても綺麗!
開花までもう少しのところをパチリ!
(どこにもピントが合っていない…)
2015年
11月
18日
水
2015年 11月号 ~理想と現実~

洗濯機の買い替えを機に大掃除に火が着いた昨年を思い出した。(スクール便り2014年11月号参照)『家に客が来る』というだけで底知れぬ行動力を発揮できることを知った。最近はイメージするだけで家事をサッサとこなせるまでに。また「タイムリミットを自分に課す」という手法も取り入れてみた。タイマーをセットし3分間で成し遂げる!とハラハラしながら片付けや洗濯(干す畳む)作業に挑むと効果抜群だ。このようなトレーニングの成果を『衣替え』で試してみることにした。タンスやケースからあらゆる物を出し切ったところで1時間経過…。トっ散らかり様に途方に暮れ1時間…。そこへ想定外の客(ガス点検業者さん)は現れるはガラクタに埋もれて見つからないタイマーはやかましいはで現実の厳しさを思い知らされたのであった。
写真の説明:
最近インターネットで購入した将棋アイテムが届いたところ
・復興支援扇子【羽生義治】・図面用紙・棋譜ノート・SHOOちゃんノート
2015年
9月
18日
金
2015年 9月号 ~先人の教え~

日本は昔から頻繁に天災に見舞われてきた。
幾度も災害に遭っている土地には、それを示す地名がつけられているという。
かつて我々の先祖は経験してきた災害の恐ろしさを後人に伝えようと地名に託した。
昨年広島で土砂崩れがあった八木地区。
昔の名は「八木蛇落地悪谷(やぎじゃらくじあしだに)」。
名前を見ただけでも危険極まりない。
「あぶない地名」をつけてくれた先人の教えを忘れてはならない。
「新夢の楽園」など不自然な地名には要注意だ。
今後移住を検討する際は、家賃や外観以外にも昔の地名やその名前の由来もしっかりと考慮に入れたい。
古地図で昔の地形などを調べて家族の命を守ろう!
というわけで「鬼怒川」を調べてみた。
普段は穏やかで絹や衣のような流れを現す衣川であるが、時には鬼のように怒り狂うような流れを表す暴れ川に変化するとあった。
ちなみにここいらは住吉村。
村だったのか…。
写真の解説:
生徒さんからのメールに添付されていた写真。
ニガウリの綿と種(ゴミとなる部分)のみでの天麩羅料理をしたところ、とても美味しかったとのこと。
緑の部分はどうしたのか凄く気になる。
2015年
3月
20日
金
2015年 3月号 ~浮世の風~

今年も桜が咲く。
冬の間も枝先に小さい蕾を付けている桜の木を毎日見上げてきた。
蕾に蓄えた花びらのせいか、まるで血が通っているみたいに木全体がこの時期薄紅に映る。
花は咲いては散り翌年また生まれ変わる。
再生という宿命を悟っているから、底知れぬ静寂さと妖艶さを帯びることができるのだろうか。
そして人は開花を待ち侘び期待に胸を躍らせる。
被災地で献花台を前に若者が悼辞を読んだ。
4年前のあの日から自分だけ生きていることに贖罪(しょくざい)の思いでいる。
あの日からずっとかなしく、悔しく、後悔と自責の念に駆られている。
東日本大震災から5度目の花が咲く。
桜は人に媚びるように下に向いて咲くという。
どうか人に上を向き空を仰ぎ底知れぬ笑顔があらんことを。
写真の解説:
白木蓮(モクレン:地球最古の花)の巨大な花びらをこそこそ拾って家に持ち帰り測ってみたところ10センチありました。
2014年
7月
19日
土
2014年 7月号 ~作戦X(エックス)~

三陸から届いた殻付き牡蠣(6月号参照)の調理に挑む!
まずは調理計画をABC三段階で画策してみた。
計画A『漁業生産組合からの指示通り調理前に牡蠣のタワシ洗浄を行う』、計画B『付属の専用ナイフで牡蠣の殻を剥(む)く』、計画C『余計な味付けはせずレモンをキュッと絞ってちゅるりといただく』。
計画Bは人生初挑戦ゆえ、You Tubeで牡蠣の殻剥き実演動画を目に焼付くまで確認し万全を期した。
さて、計画は順調に遂行されていたように思われたが、早くも計画Bが危ぶまれる非常事態が起こってしまった!
牡蠣にナイフが刺さらない。
がむしゃらにナイフを突きまくること30分。
体力も気力も限界、もうこうなったら生ガキを諦めカキフライかカキグラタンに作戦を変更するしかない!
だがその前に殻を…(T_T)と少々錯乱状態に陥った。
その時、三陸から届いたレシピの頁末を見て思わず息を飲んだ。
速やかに『簡単 カキの酒蒸し』に作戦を変更!鍋に牡蠣を放り込み酒で蒸すこと30分。
熱々ぷりぷりミルキー牡蠣の出来上がり♥
旨(うま)い!
こんなに旨い牡蠣がいただけ更に復興応援となるのであらばお安い御用だ!
殻が上手に剥けるよう応援してほしい。
写真の説明:
頑固な牡蠣殻がようやく開いてぷりぷりのところをパチリ。
2014年
6月
21日
土
2014年 6月号 ~復興のきざし~

宅急便の荷物が届いた。
両手に抱えられている発泡スチロールの箱を目にした瞬間、その中身が牡蠣であると察した。
予感は的中!
『三陸牡蠣復興プロジェクト』への参加から2年、岩手県の三陸から牡蠣が届いたのは先月のことだった。
世界三大漁場である三陸沿岸部は東日本大震災で瓦礫の戦場と化した。
全てを失いゼロ以下からのスタートはどれほどの苦難を強いられたかは想像を絶する。
全力で牡蠣の再生から出荷に関わってきた方々の想いと殻付き牡蠣20個、保冷用に敷き詰められた氷の詰まった発泡スチロールの箱をしかとこの手で受け止めた。
被災地の復興を祈ることしかできないもどかしさがあったが、『食べて応援』という形で少しは貢献できただろうか。
牡蠣と一緒に生産者様からの感謝の手紙が同封されていた。
三陸沿岸漁業の復興の証でもあるこの目の前の牡蠣に恥じぬよう今晩全力で調理に挑むことを固く誓い、手紙を握りしめる手に一層力が入るのであった。
つづく。
図の解説:
この図をクリックすると『三陸牡蠣 予約注文』画面に移動するように設定されている。
2013年
9月
17日
火
2013年 9月号 ~カウントダウン~
2020年東京オリンピック決定バンザ~イ!
日本がオリンピック開催国となり興奮している。
あと7年の間に何とか聖火ランナーに選抜されたいものだ。
聖火リレーは東北から出発だ!
被災地における着工のメドが見えてきたのが嬉しい。
道路、線路、地盤、住居の建設、完全復旧東京オリンピックにあり!
開催まであと2508日
2013年
3月
13日
水
2013年 3月号 〜食べて応援〜

「三陸牡蠣復興プロジェクト」から復興かきオーナーへと配信される不定期メールが届いた。
実は1年前「オーナー」の称号欲しさに・・・ではなく、津波で全てを流された三陸沿岸部のカキ生産者さん達の呼びかけで、再起にあてる資金面の支援を第1の復興支援とし、カキを育て第2の復興支援として出荷を目指すというものであり、カキを出荷できるまでのお手伝いにオーナー制度という形で参加させてもらった。
今しがた届いたこのメールを開く瞬間、ついにカキ配送のお知らせが来たか?!と予感した。が、内容は出荷見込みや生産者の声だった。
牡蠣を通じて被災地の現実をうかがい知ることができた。
牡蠣は海上で養殖施設を必要とし、陸上では浄化、加工、選別などの作業施設が必要だが、地盤沈下で作業施設建設には港のかさ上げ工事も必要だ。
全く手つかずの場所や電気や水道が通じていない地域がまだあるとのこと。 地域によって復旧に大きく差が出てきているらしい。
防波堤も無く波風をまともに食らう海沿い、夜になれば電灯ひとつ無い暗闇での作業は危険を伴う。
どうかお体を大事に働いてください。
カキ生産者皆様の安全とご健康を心よりお祈りいたします。
震災から3度目の春。
自宅に美味しいカキが届き、舌鼓を打つその日が待ち遠しい。
私の中で震災はまだ続いている。
2012年
11月
13日
火
2012年 11月号 ~大槌のワカメは絶品!~

12mを超える大津波は高さ6mの防潮堤を破壊した。
凄まじい亀裂が走る波止場を歩き、時折段差に躓きながら美しい三陸風景を眺める。
全てを津波で流された漁協施設、丸められた魚網、人気のない漁船。
目の前に広がる青く静かな海はまやかしか。
静けさの中で、カモメの群れだけがちょろちょろせわしない。
地盤沈下のせいで波が起こると水が容易に地面に這い上がる。
濡れまいとカモメも必死なのだろう。
そうか、港に帰る大漁の漁船からのおこぼれに与ろうと、今か今かと沖を見据えていたんだね。
かつては栄え、町を潤した漁協組合は先月、ついに破産に追い込まれた。
東北の冬は長い。
仮設住まいで多くの方が不自由な思いをされている。
狭くプライバシーのない状態、玄関のトタン板の隙間、今だこれが現実…。
こんな時でも自然や先祖を敬い祭り行事で地域を盛り上げ、町の再生に情熱を傾ける人たちの姿は尊く素敵だ。
復興までの道のりが長期に渡ることは想像に難くない。
今まで以上に被災地支援が必要になる。
被災地のことを心に留め風化させないことが重要だ。
2012年
10月
10日
水
2012年 10月号 ~がんばっぺし!大槌~

大津波にのみ込まれ壊滅した現在の大槌町の街を歩く。
震災から1年半が経ち、新聞やテレビで見た瓦礫の散在は人や車が通れるほどに片付いている。
コツコツと作業を続けているボランティア団体は後を絶たない。
鉄筋構造ゆえにかろうじて残った建物の損傷は惨い。
一見見通しのよい広大な沿岸の荒れ地。
雑草が隠している間仕切りのようなコンクリートが戸建住宅の土台だと気付いた時、そこに手向(たむ)けられた花束が次々に目に飛び込む。
再起した喫茶店に入り注文したコーヒーとケーキは思いのほか美味しかった。
「ここは街の中心でとても賑やかだったのよ、隣もあっちも銀行で病院もあって人も沢山住んでいてほら、あそこは大槌の駅があってとっても便利で賑わって、とても…」と窓の外を指示しながら堰を切ったように説明するオーナーの赤崎さんの瞳には、以前の街並みが映っている。
沢山の人が誤って逃げた方角は見るのも嫌と言った。
駅はもうない。見えるのは崩壊した防波堤や橋脚。
行き場もなく積み上げられた瓦礫の巨大さはショベルカーやクレーンをも小さく見せる。
いつの間にか奥の席に座る赤崎さんは、両手を膝の上に置いてじっと窓の外を見つめている。
先ほどとは別人のように悲しく、静かだった。
ここに住み日常を送る人たちは、目が覚めれば嫌でも現実と向かい合う。
人間は忘却の生き物である。されど忘れることさえ許されない。
この震災を教訓とし決して忘れるなかれと言うは易い。されど耐え難きこと。
つづく。
2012年
9月
16日
日
2012年 9月号 ~とにかく生きよ~

9月1日がなぜ「防災の日」なのか知らなかったのは私だけだろうか。
「防災の日」をネットで調べてみた。「1923年9月1日午前11時58分に地震が発生し未曾有の被害をもたらした。のちに関東大震災と呼ばれる。」
そうだったのか。知らなかった…。
そして関東大震災を教訓として1960年(昭和35年)9月1日の「防災の日」が制定された。もとより9月は台風に見舞われることが多いので心構えの意味も含まれているらしい。
昼夜問わず起こり得る自然災害を未然に防ぐ手立てはない。平時より避難袋を抱えて過ごせと言うのか?!(←心構えのない発想)
あるテレビ番組を見た。1年半前の地震と津波を体験し乗り越えた岩手県釜石市の小学生がこう言った。「今か100年後に同じ事が起きた時、一人でも多く生きていればいい」この子供達は地域のハザードマップ作成や災害対策を懸命に取り組んでいる。無意識に後世へと継承している。国土交通省の発表したハザードマップを新聞で眺めてチラリとでも諦めを覚えた己を恥じた。
 パソコンBini元住吉スクール 真理子先生のつぶやきコーナー
パソコンBini元住吉スクール 真理子先生のつぶやきコーナー